今回は相談事例を通じて、遺産分割協議ができない場合の相続登記の方法について、ご紹介します。
私の父は10年前に亡くなりました。相続人は私と母と姉の3名で、遺産は自宅の不動産と預貯金100万円でした。父の遺産はすべて私が引き継ぎたいと思っています。
しかし、亡くなった当時から現在まで、不動産の名義変更をすることなく、不動産の名義は父のままとなっています。
相続登記義務化が始まったと聞き、早急に対応をしたいのですが、私の母は認知症のため、遺産分割協議をするには後見人の選任が必要といわれました。後見人を選任するには費用も時間もかかると聞きましたので、どうしたらよいか悩んでいます。相続登記の義務違反とならないための方法はありますでしょうか。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は、3年以内に登記をしなければなりません(不動産登記法76条の2)。しかし、ご相談の事例のように、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合等には、遺産分割協議ができずに相続登記ができないといったことが考えられます。
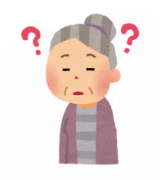 ご相談の場合、1つ目の方法として、ご相談者様とお姉様は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)という手続きをとることで、義務を果たすことができます。ただし、お母様は、この手続きをすることができない状況と思われます。
ご相談の場合、1つ目の方法として、ご相談者様とお姉様は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)という手続きをとることで、義務を果たすことができます。ただし、お母様は、この手続きをすることができない状況と思われます。
2つ目の方法として、「法定相続分での相続登記」をすることで相続登記の義務を果たすことができます。
ご相談の場合、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様が4分の1の法定相続分となりますので、その内容で相続登記(所有権移転登記)をすることになります。この手続きは、相続人の1人からでも手続きができるため、お母様が認知症であっても登記をすることが可能です。
ただし、ご相談者様のご希望である、ご相談者様がおひとりで所有者となる登記は、この時点ではできません。後日、お母様の成年後見人が選ばれ、成年後見人とご相談者様、お姉様との話し合いがまとまり、遺産分割協議が整った場合に、「所有権更正登記」をして、遺産分割協議のとおりの内容に「更正」することができます。
従来から、法定相続分での登記の後、遺産分割の登記をすることは可能でしたが、令和5年4月1日より登記手続き方法が簡略化されました。
例えば、ご相談者様が単独で不動産を取得するという内容の遺産分割協議が行われた場合、従来は、不動産を取得する方だけでなく、不動産を取得しない他の相続人の協力(登記申請書または委任状への実印の押印、印鑑証明書の提出)が必要でしたが、現在は、不動産を取得する方(ご相談者様)からのみの申請でよいということとなりました(令和5年3月28日法務省民二第538号通達)。
また、登録免許税についても、従来は不動産の固定資産税評価額の0.4%により算出されましたが、不動産の個数1個につき1,000円となり、金銭的な負担も軽減されました。
具体的なご事情により、どの方法を選択された方がよいかは異なりますので、詳細はお近くの専門家(司法書士)にご相談ください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 法定遺言事項と付言2026/01/20
- 成年後見制度とは2025/12/20
- 相続等により取得した活用見込みのない土地の処分方法2025/11/20
- 認知症の疑いがある方でも遺言作成は可能か2025/10/20
- 高齢の親の財産を子が管理するための留意点2025/09/20
- 死後離縁2025/08/20
- 数次相続2025/07/20
- 死後認知2025/06/20
- 遺言書の封印を解く前に知っておくべき手続き2025/05/20
- 相続登記時に申出が義務化される生年月日等2025/04/20
- 米国に相続財産があり国籍の確認が必要な場合の相続手続き2025/03/20



